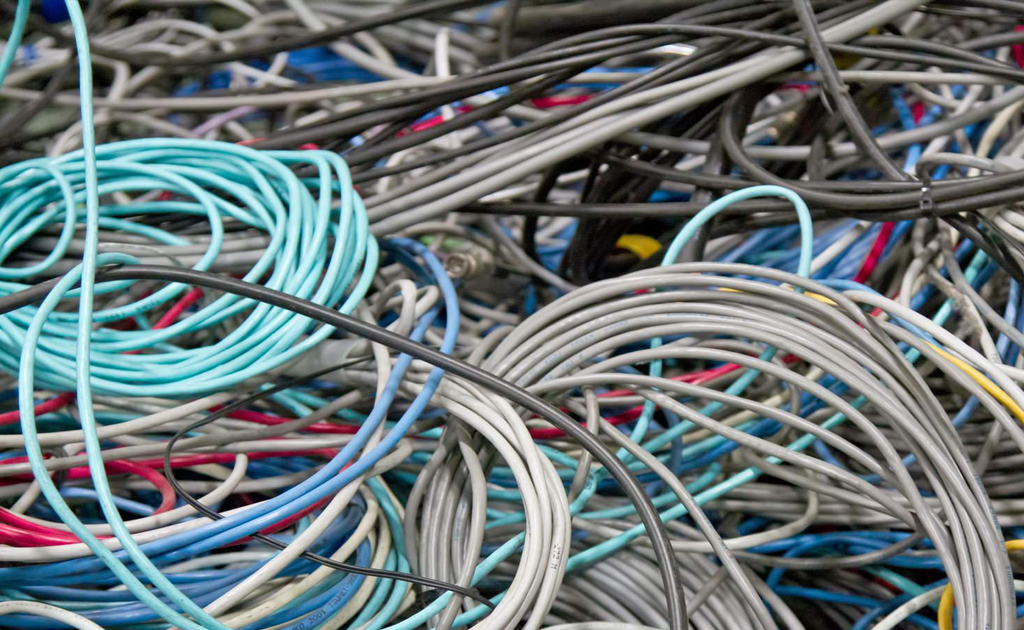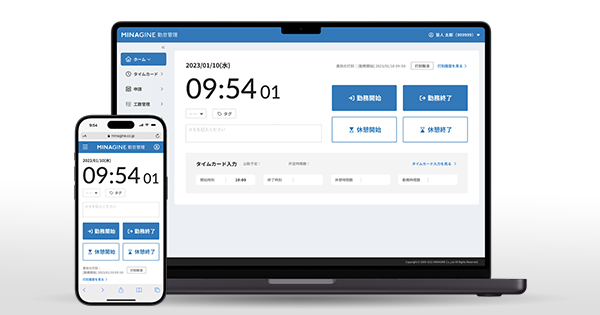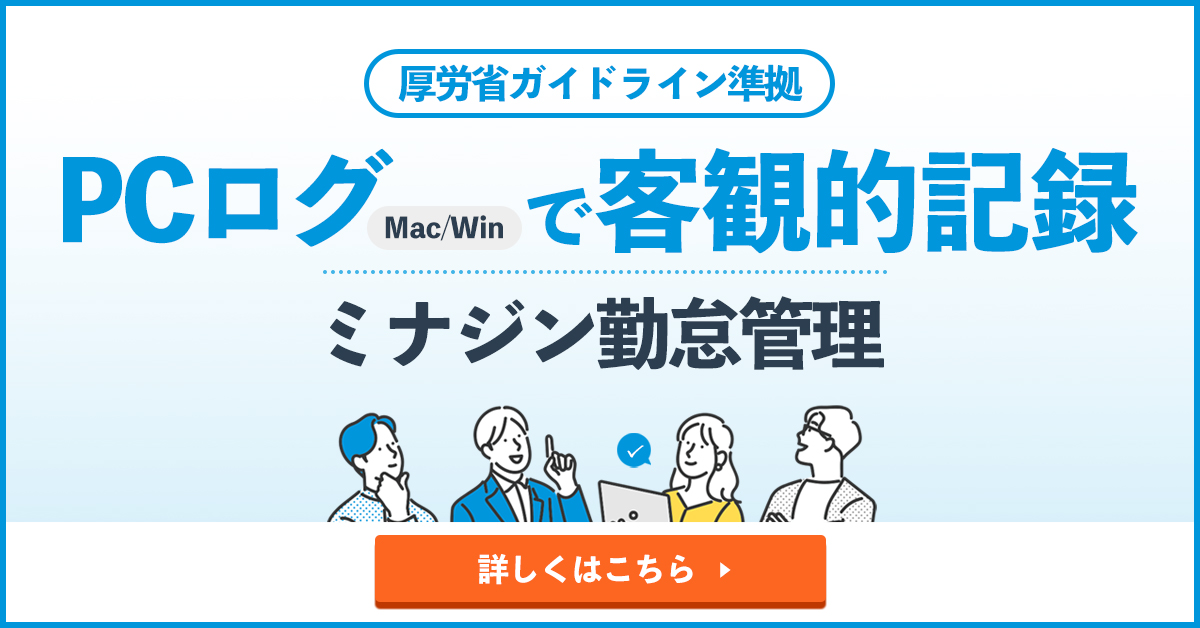勤怠業務を手放すと人事は何に時間を使えるのか ~人事部の働き方改革を実現するアプローチ~

多くの企業において、人事部の毎月のルーティンワークは「勤怠業務」に縛られています。
月初の集計、打刻漏れのチェック、未申請者への催促、休暇や残業の承認確認、監査対応用のデータ整備…。これらは毎月必ず発生するため、担当者や管理職の時間を大きく消費します。
本来、人事部が担うべきは「人と組織の価値を最大化する仕事」です。採用や育成、制度設計、組織開発といった戦略的な取り組みが企業の競争力を支えます。しかし実態として、多くの時間が勤怠業務に費やされ、戦略業務へのシフトが進まないという声は少なくありません。
「勤怠業務をどう効率化するか」ではなく「そもそも手放すことができるのか」。ここに、人事部の働き方改革のヒントがあります。
勤怠管理のスタンダードを提供するトータルアウトソーシングサービスのご紹介資料です。
目次
勤怠業務に潜む”時間の罠”
勤怠管理は繰り返しの一見シンプルな業務に見えますが、実際には複雑で負担の大きい業務です。以下に典型的な課題を整理します。
工数の大きさ
- 担当者1人あたり月20~30時間程度を勤怠処理に費やすケースも珍しくありません。勤怠修正作業、催促、締め作業、給与データ加工、システム設定変更などなど
- またまとめて時間がかかるというよりは勤怠締め1週間前にばらばらとイレギュラーな処理などが発生することで他作業に影響します。
- 年間で換算すると数百時間に及び、部門全体で見れば人件費換算で数百万円規模となることも。(作業工数・離職・採用コストなど)
属人化リスク
- 前任者が設定したルールやシステムがブラックボックス化し、異動や退職の際に引き継ぎが難航する。
- 「誰がどう処理しているか」が不明確なまま運用が続き、突発的な欠員に対応できない。新たな人員が確保できるまで勤務歴が長い管理職が巻き取らざるを得ない。
- 管理部員の採用が難しく、採用しても属人的な業務が原因で退職に至る。
法令・監査リスク
- 36協定違反や休憩時間不足、未払い残業といった労務リスクの温床になりやすい。
- IPO準備や労基署調査の際に、勤怠データの不整合が指摘事項となる。
モチベーションの低下
- 勤怠業務は単調で反復的な作業が多く、人事担当者のモチベーションを下げる要因となりえる。
- 「自分のキャリアに繋がらない」と感じ、離職につながることもある。
- システムの設定や法対応が完全に出来ているか不安なまま毎月の給与計算を迎えるというストレスもあります。
このように、勤怠業務は単なる作業コストだけでなく、組織全体に潜在的なリスクを抱え込む要因になっているのです。
勤怠業務を手放すことで得られる「時間」
もし勤怠業務にかかる時間を削減できれば、その分を人事本来の戦略業務に充てることができます。ここでは代表的な活用先を挙げます。
採用強化
- 候補者対応のスピードを上げ、応募者体験を改善する。
- 自社の魅力を発信する採用ブランディングに力を入れる。
- データ分析を活用し、採用チャネルの最適化を図る。
人材育成・制度設計
- 研修プログラムを体系的に設計し、実行につなげる。
- 評価制度を定期的に見直し、組織の成長段階に合わせて更新する。
- 社員のキャリアパスを整備し、長期的な成長を支援する。
組織開発・エンゲージメント向上
- 従業員サーベイを定期的に実施し、改善策を素早く打ち出す。
- 離職予兆を早期に把握し、定着率改善につなげる。
- ダイバーシティや働き方改革を推進し、組織の柔軟性を高める。
3.4 経営への貢献
- 勤怠データを活用した人件費・労務リスク分析。
- 経営層へのレポートを充実させ、意思決定を支援。
- 戦略人事としての存在感を発揮する。
勤怠業務の削減は単に効率化ではなく、「人事が本来の役割に立ち返るための時間を創出する」ことに意味があります。
外部委託(BPO)という選択肢
勤怠業務を効率化・軽減する方法はいくつかあります。
- 自社対応(内製化)
- 社内で人員を増やし、体制を強化する方法。
- ノウハウは蓄積できるが、コスト増・属人化のリスクは残る。
- システム導入による自動化
- 勤怠管理システムを活用し、自動計算や打刻チェックを導入。
- ただし、運用ルールの設定や例外対応は人手に依存し続ける。
- 外部委託(BPO)の活用
- 専門チームに業務を委託する方法。
- 属人化リスクを解消し、法令対応やチェック精度を高められる。
- 一方で依存度が高まるため、委託範囲の見極めが重要。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、近年は「システム+BPO」を組み合わせたハイブリッド型が増えています。特に外資系企業やベンチャー企業ではその動きが顕著です。
ケーススタディ:中堅企業の事例
ある従業員数150名規模の企業では、人事部2名が毎月の勤怠締めに合計40時間以上を費やしていました。特に未入力者への催促や不備修正、タイムカード確認に追われ、本来やりたい制度設計や採用業務が後回しになっていたのです。
外部委託を導入した結果、勤怠業務の工数は1/3になり、浮いた時間を評価制度の改善やルール整備に振り向けることができました。結果的に離職率が下がり、経営層から「人事部が組織の成長に貢献している」との評価が高まったといいます。
このように、勤怠業務の外部化は単なる効率化ではなく、組織の成長戦略と直結する施策になり得るのです。
まとめ:勤怠業務を“手放す”という発想を持つ
勤怠業務は、誰かが担わなければならない業務です。しかし、それを「人事部自身が抱えるべきかどうか」は別問題です。
人事部が本当に注力すべきは、採用・育成・組織開発といった「人を通じて会社を強くする仕事」です。
勤怠業務を効率化するだけでなく、外部化することで「時間の余白」を生み出す。そこから初めて、人事が経営のパートナーとしての役割を果たせるようになります。
今、人事部に求められているのは「勤怠業務をどのように効率化するか」ではなく、「勤怠業務をどのように手放すか」 という視点なのです。
勤怠管理のスタンダードを提供するトータルアウトソーシングサービスのご紹介資料です。