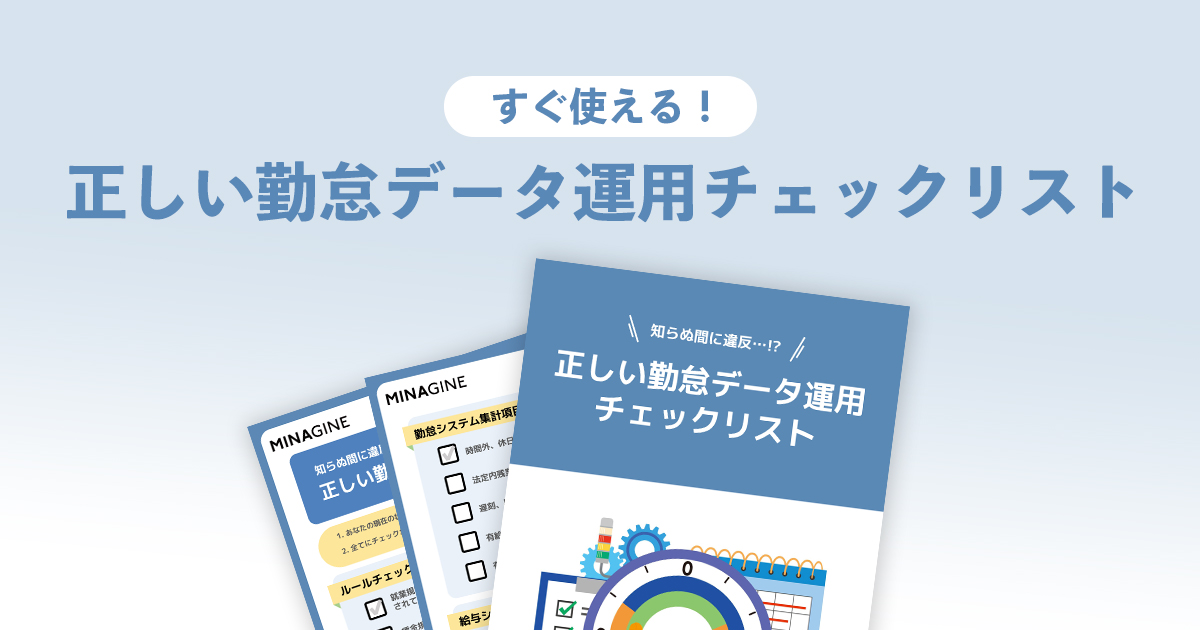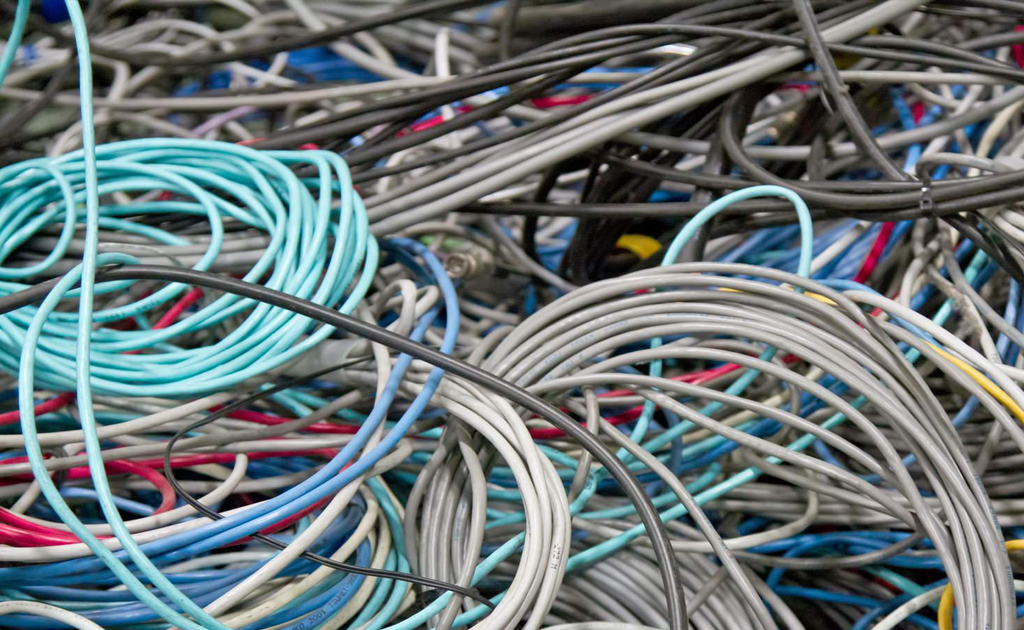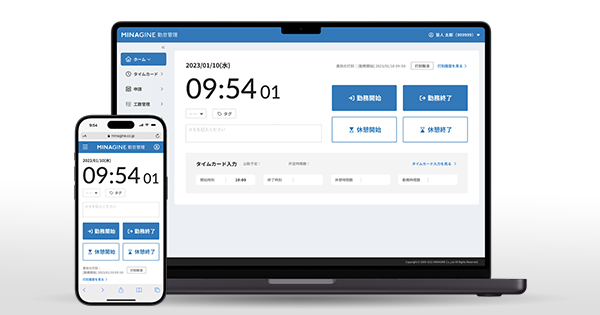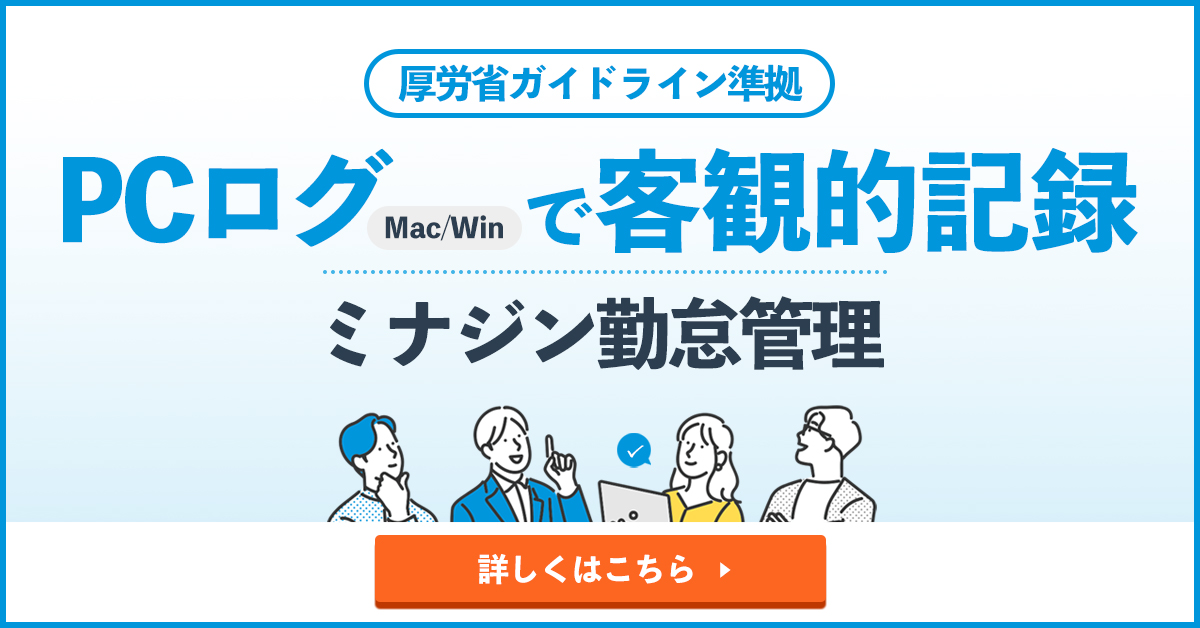勤怠管理システム乗り換えの落とし穴3選 ― よくある“失敗あるある”とその回避策

企業が勤怠管理システムを乗り換える理由はさまざまです。
「今のシステムのランニングコストが高い」「法改正に対応できない」「サポートが不十分で困っている」など、不満を抱えて乗り換えたいな~と考え始めることが多いのではないでしょうか?
しかし、「なんとなく今よりよくなるはず」と曖昧な期待で導入を決めてしまうと、結局同じ問題が繰り返されてしまいます。システムを変えただけで課題が解消するわけではなく、むしろ新たな混乱を生むケースも多いのです。
そこで本記事では「勤怠管理システムの乗り換えを検討する企業が陥りがちな失敗あるある」を3つ紹介し、実際の事例とあわせて回避策を解説します。
本チェックリストでは、ルール整合性や勤怠データ、集計や給与計算との連動性など多角的に自社運用をセルフ診断できます。
目次
失敗あるある① 前任者ブラックボックス問題
あるある内容
前任担当者が設定を行ったものを「操作方法」だけ引き継ぎ、中身を誰も理解できない状態でシステムが使われ続けるケース。
たとえば、勤怠データ集計がどの計算式で導き出されているのか不明、休暇が自動で付与されるはずなのに反映されない理由が説明できないなど、担当者が変わるたびに継承される情報が薄くなり謎が増えていきます。
起こりがちな結末
設定の仕組みが分からないまま時間が経過すると、法改正や就業規則の変更対応が新しいパンドラの箱を開けることになり億劫になります。その結果、給与計算で誤りが発生し、従業員からの問い合わせにも答えられず、現場が混乱してしまいます。最終的には「このシステムはうちには合わない」と判断され、また新しいシステムを探す羽目になることも少なくありません。
回避策
・システムの設定を一人に任せきりにせず、設定経緯や仕様を文書化して共有
・メーカーやベンダーに設定を依頼し、初期設定の背景を記録に残す
・定期的に設定内容を棚卸しする運用を取り入れる
失敗あるある② 一部の特殊ルールにこだわりすぎて要件定義あまあま問題
あるある内容
「代休を5分単位で取得できるようにしたい」「部署ごとに独自ルールを細かく再現したい」など、細部の要望にとらわれすぎて全体設計が甘くなるケース。
起こりがちな結末
特殊なルールを無理にシステムへ反映しようとすると、例外対応が次々と積み重なり、システム自体が複雑化してしまいます。すると、結局はエクセルなどで手作業による補完が必要になり、「システム化した意味がない」と担当者が嘆く状況に。さらに、ルールの解釈が曖昧なまま設定されると法的な整合性に問題が出たり、後任の担当者が理解できずに混乱が長期化することもあります。
回避策
・例外は簡素化するのを原則に!
・「システム導入=ルールを見直すチャンス」と捉え、プロセス改善に取り組む
・「うちだけの特殊ルール」を追求しすぎず、業界標準や法令準拠を優先する
失敗あるある③ システムへの過大期待問題
あるある内容
「システムさえ導入すれば、自動的に労務管理がすべて解決する」と経営層や現場が誤解するパターン。
起こりがちな結末
システムが導入されたからといって、従業員の打刻意識や申請ルールが自動的に改善されるわけではありません。教育やルール整備を軽視すると、打刻漏れや申請不備が相次ぎ、最終的に「前より手間が増えた」「管理職に質問がくる」と現場が不満を募らせます。経営層も「投資したのに効果が出ない」と失望し、導入自体が無駄だったと評価されかねません。
回避策
・システムはあくまで“道具”であり、運用が成功のカギと理解する
・導入と同時に社内規程や運用ルールを見直す
・取得できたデータを活用して、働き方改革や経営判断につなげる
まとめ
勤怠管理システムは「乗り換えればすべて改善する」とは限りません。むしろ準備不足のまま進めれば、再び同じ問題に直面することになります。
成功の鍵は以下の3点です。
・ブラックボックス化させない
・大きな目的を見失わない
・過大期待を避ける
まずは現行運用を棚卸しし、どこに問題があるのかを明確にすることが、次のシステム導入を成功に導く第一歩です。
「自社ではどう進めればいいかわからない」という場合は、ぜひkubellパートナーにご相談ください。壁打ち相手として最適な導入計画づくりをサポートします。
本チェックリストでは、ルール整合性や勤怠データ、集計や給与計算との連動性など多角的に自社運用をセルフ診断できます。